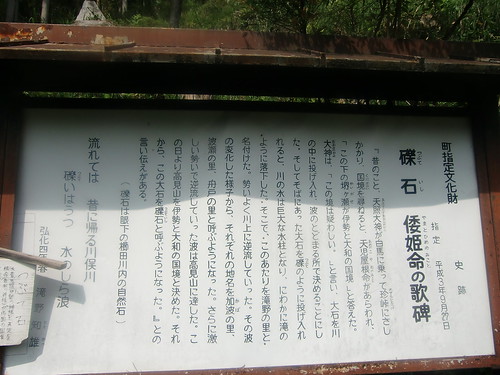岩石信仰に関する新たな論考が世に出されました。
民俗学者の倉石忠彦氏が『長野県民俗の会会報』第40号(2017年11月刊)に発表された「石のイメージ―石神と道祖神―」です。
同好のみなさまに向けて、当論考の概要を節ごとに紹介いたします。
岩石信仰の深みを知る一つの書として、広く知られれば幸いです。長文となりましたので、ご関心のある方はお時間のある時にお読みください。
一 問題の所在
倉石氏は長年、道祖神について研究を続けてきた。
その中で、道祖神が石の形で表されるケースに出会う。
ただし、道祖神=石ではないのと同様に、石=道祖神でもないことは承知の上で、道祖神と石神という2つの信仰はどのように相互影響しあって、現在のように境界線を引きにくい混然一体の存在となったのか。
道祖神研究の専門家である倉石氏が、道祖神なるものをさらに追究するため、石に対して日本人がいかなる心性をもって付き合ってきたかという「石のイメージ」について取り上げたのが本稿である。
二 「石」の認識
倉石氏は、ここで興味深い前提をのべている。
石は地球上に偏在しているからこそ、人が石を意識することは逆に少ない。いわゆる空気のような存在ということである。
「意識しない=生活世界において存在しない」という図式を提示している。
石に意識することが、石へのイメージの始まりということになる。
石をイメージすることで、石に対してあらゆる感情が生まれる。
石への信仰も、そういった感情のうちの一つとして把握することである。
倉石氏は、門外の考古学はあえて省いて、文献上で日本人が石を始めて意識した記述を取り上げていく。
その最初は『古事記』となる。
イザナギとイザナミの国造り神話において、国々を産んだ後に生まれた石土毘古神と石巣比賣神の二柱。
物語順としては、これが石を意識化した初出である。
少なくとも、『古事記』編纂時点では「石・土」「石・砂」という組み合わせで、生活世界の中で意識されていたことは疑いない。
ここで倉石氏は、一つの私見を提示している。
――「ここに認識されている『石』は、具体的な機能や形を持った存在としてではなく、無機物として遍在する風景の一部としてであり、いわば景観としての存在だった。」
一つの考えとして理解できるが、そうとも限らないのではないだろうか。
石土毘古神・石巣比賣神という神名として登場するのであれば、単なる風景や景観のイメージではなく、神格化されたモチーフに石が使われていることに他ならないのではないだろうか。
また、物語順としてはこれが初出かのように思えるが、『古事記』は「記述された順=時代制作順」という理屈と証明されるものではなく、記述が冒頭だろうと最後の方だろうと、基本的には時代の先後順は不詳であり、同時期として一括すべき性質のものだろう。
現に、倉石氏はそのすぐ後で、同じ『古事記』の「湯津石村」「石折神」、それに対応する『日本書紀』の「草木・沙石の自づからに火を含む縁なり」といった記述を紹介し、神話の中で石が火と結びつき、石が火の神のイメージを含むことを指摘している。
そうであれば、『記紀』における石の記述は、風景・景観のイメージとしても、神格化したモチーフのイメージとしても扱われているという理解で良いと思う。
なぜ、石を結びついたのはあえて火だったかは議論の余地があろう。
倉石氏は「生活に欠くことが出来ない火」と表現したが、それがなぜ石で代表されるのか、単にこれまでの民俗学の蓄積による竈神的な発想、性神的な発想などの中だけで可能性を狭めたくはない。
三 遮る「石」
『記紀』の黄泉国神話に登場する「千引の石」。
黄泉の国とこの世の境界を塞いだ石である。
これは「道返之大神」「黄泉戸大神」と神格化されていることから、石は「返」「戸」の性格を有し、遮る機能を持った石として、単なる景観を超えたイメージを込めていると言える。
記紀神話には同様の用例として天岩戸があり、ここで傾聴すべきなのは大舘真晴氏の研究(同氏「いわと」『万葉集神事語辞典』2008年)を引用して、『万葉集』の「岩戸」の用例は ①高天原の出入り口にある戸 ②墳墓の出入口にある戸 の2種類があることを指摘したことである。
黄泉国神話の千引の石に通ずる、生者の世界と死者の世界を分かつ扉としての石のイメージ。
重い石だからという単なる戸としてだけではなく、ここには、重さという石本来のイメージからは離れた聖俗の結界のイメージが読み取れる。
天岩戸の高天原の出入口ということも考え合わせれば、正確に言えばあの世だけではなく、異界・他界との境を担う働きを帯びていると認識した方がより適切だろう。
一方、宗教的なイメージとしての石ばかりを取り上げるのは、一面的に過ぎる。
倉石氏は『万葉集』や『祝詞』『出雲国風土記』『日本霊異記』などの文献のなかで、旅の道中や開墾の中で大きな石が障害となって難儀している旨の記述を複数紹介している。
景観としての岩石が、何かしらの作業の途上で「障害物」となった場合、景観としての存在を超えた意識の対象となることを指摘している。
元々は重く大きいという石の性質から由来する「障害物」という性質なのかもしれない。
しかし、小さい石でも「遮る」「塞ぐ」という用途を持つ記述として、神功皇后の鎮懐石伝承にも言及されている。
鎮懐石は、腰にしのばせるほどの小さな石だが、これで陣痛を鎮め出産を「遮った」機能を持つ。
石の大小からは解き放たれた次元でのイメージが、当時すでに進んでいたことが示されているとみて良いだろう。
四 モノとしての「石」
倉石氏は『広辞苑』を引きながら、石の概念について次のように規定している。
- 巌(磐石):石の大きなもの。その中でも、それ自体に関心があるわけではないが、風景の中で意識されている岩のことを特に巌と呼ぶ。
- 岩:石の大きなものという意味では上の巌と同義だが、風景としての巌から一歩進んで、特定の意識・関心の対象となったものを指す。
- 石:岩より小さく、砂より大きい塊。
- 礫 :小さい石。
- 砂:細かい岩石の集合。
当然ながら、倉石氏もこの分類は数値化できるものではないということを承知の上で述べている。
倉石分類の特筆すべきところは、巌と岩の区別を意識の段階で分類できたという点である。
管見では初めて見る着眼点で、確かに有用な差であると目が開いた思いがした。
倉石氏は、さらに注意深く、風景・景観に溶け込むものは巌だけではなく、石や礫においても歌や記述の中で景色のモチーフとして取り上げられていることを紹介している。
このような石は、目に入ったり歩いたりする中で目に入る景観として意識され、無意識化からは浮上する存在だが、あくまでも無機物のモノ(物体)の一部としてあるにすぎないと、意識の段階について注意を促している。
これについては、私は個人的には「景観=無感情」とは思いにくく、歌で詠まれるなどは美的観賞の価値観が入り交ざっているのではないかと思う。
倉石氏が先述した「障害物」として登場する石たちも、それが宗教的感情と相通ずる「塞ぐ]意識の一例として聖と俗の狭間に立つのだとしたら、それはもうすでに単なるモノを超えている意識なのではないかとも思うのである。
倉石氏が指摘するような、いわゆる本当の風景・景観とは、おそらく文献に記述されないレベルでの無意識であり、文献研究からは追えないような段階のものではないかと考えるが、いかがだろうか。
また、倉石氏は巌・岩・石・礫までをいわゆる石の範囲としているが、砂を紹介しながらなぜか砂を除外している。
かつて野本寛一氏が砂は石の極小と表現したことを取り上げるまでもなく、砂はそれ単体のイメージだけではなく、立砂の存在や砂を用いた神事があるように、砂を集合させて石に類する造形で祭祀物にも昇化している。そこに、砂と石との差はないはずだ。
五 コトとしての岩石
ここから、本稿のメインとも言うべき「モノ」と「コト」の概念がさらに深化する。
誤解がないように、倉石氏の記述をそのまま引用する。
――「モノとしての石が、コト(行為)によって、特定の役割を果たしたり、意味を持ったりすることがある。」
これを以て、モノとしての石はコト化するというのが本稿で展開される核心部である。
倉石氏はその例として、井戸や墓や城などの構造物をつくろう(=コト)とした時に、モノだった石が建材としてコトになるとみなす。
構造物の建材は人工でなくても、自然石の中でもたとえば天皇や貴人が伝説・祭祀の中で立つ「お立ち石」があるという。
石に立ったり上ったりするという人間の行為(コト)が、なぜか儀礼的な行為や象徴的な行為として登場する。
神の来臨する磐座のようなものも、同じく神の行為(コト)があって、モノとしての石が宗教性や重要性を帯びる。
これらをコトとしての石としている。
六 コトとモノとしての「石」
動物や生活用具などの事物に形が似ている石が、過去の伝説や色々な事物に擬せられることがある。
『出雲国風土記』に登場する猪石の伝説や、神や貴人の食べ物の粒が小石になって残るという記述、星が地上に落ちて石となったという話は、石が過去のコト(行為)に関わる記憶と結びつけられることで、モノを超えた意識対象となった。
これらについては、私もかつて岩石祭祀の分類で「聖跡型」として規定したグループの事例と重なるところがあるが、倉石氏はこれらをモノとコトという2つの位相で把握を試みている所に新しさがある。
七 ココロとしての「石」
さらに、ここでモノとコトに次ぐ次の位相として「ココロ」の概念を倉石氏は取りあげる。
整理すると、モノは景観の一部としてとけこむもの、コトは行為の対象となったもの、ココロは人の感情・精神に作用する存在となった石である。
たとえば日本神話の石長比賣は、「命長かれ」と祈って差し出された存在であることから、石を恒久不変の力を持つ存在としてまで特別視した例とされている。
君が代のさざれ石や、長野県玉依比売神社の児玉石神事、全国各地の石成長譚なども、石が成長したり新しい命を生みだしたりするという点で、石の持つ性質がとうとう人の感情の領域まで影響したココロの事例である。
それの最終的な姿が、石神である。
ここでいよいよ、道祖神との比較で取り上げられた石神信仰が登場する。
人にとっての精神的なよりどころとしての影響を最大限に放つ石神というイメージは、まさに石のイメージがもっともココロの領域に進んだ存在なのだということを、倉石氏は示したかったのではないか。
第三節の「遮る石」 で登場した宗教的な石たちも、論文の最初の方で登場したから混乱しやすいが、人の感情に働きかける力を持っているという点でココロに昇化している石も入っていると言えるだろう。
八 石と民俗文化
ここで考察の方向は変わり、これまでの民俗学研究の中での石を概観する節を挟む。
柳田國男・折口信夫ほか民俗学の大家たちの研究を引きながらも、倉石氏が提言する重要な問題提起とは、「その関心は、信仰的な側面に引かれがちであった」という一文に集約されている。
信仰だけが、伝承や文化を代表するものではない。
生活文化のあらゆる事象の中の一つに、信仰という世界があり、 石も生活文化全体の中で改めて調査・研究され、それを経た上で信仰の石も位置づけられるべきではないか、と警告するのが倉石氏の問題提起だ。
これについて、私も深く同意する。
信仰を研究するために、信仰のことだけを追い続けるのは早計である。
信仰以外のあらゆる解釈可能性を認知していないと、信仰と信仰でないものの違いを正確につかむことは難しいのではないかと、私も2005年に書いた論考の中で触れたことがある。
私の2011年の拙著も、倉石氏にそのような文脈で「『石』一般の中に信仰対象の『石』を位置づけているところに、従来の研究にはなかった新しい視点」が見られると評価をいただいたが、私自身、いまだ信仰を研究するために信仰分野から手を広げた生活文化全体に調査を広げられていないのが実情である。いまだ理念だけ先走っているのである。
それほどに、信仰研究は遠回りしないと難しい。
(私が現在、石の哲学を追いかけているのはこの考えの下にある)
また、私を取り沙汰するまでもなく、このような生活文化全体で位置づけようとした石へのまなざしは、すでに野本寛一氏『石と日本人』(樹石社、1982年)の中に見つけることができる。
私も指摘したが、倉石氏が指摘するように野本氏の石に対する記述の時々には、信仰ありきで引きずられた飛躍が見られることは否定できないが、それは半ば時代的制約のようなものとみなせる。野本氏の最大の関心は信仰心にあったが、石へのまなざしは生活用具まで抜け目なく網羅し、それこそ石どころか砂までおよんでいた一面も伝えておきたい。
いずれにしても、生活全体の中で「石」を位置づけなおす取り組みを始めなければいけない。
倉石氏はその位置付けを次のようにまとめた。
――「『石』は、人の外界に対するモノ・コト・ココロという三様の認識の仕方によって、異なる様相を呈するのである。それは三つの様態が、入れ子状に認識されるのではない。「石」には三様の様態が内在し、認識の仕方によって三様の様態の内のいずれかの様態が、人との関わり方によってその都度顕在化するのである。」
実際の論文には、これを図解した「石」のイメージ関係図が掲載されている。
わかりやすい例として、倉石氏は「祭りにおいては神として祭祀対象とされる『石』が、普段は景観としても認識されず、モノでもなく、コトともかかわらない」ケースを挙げている。
私も、この現象をどのように説明すべきかを考え、拙著で岩石の認識段階と機能分類のなかで、それが複数の要素を持ったり時期ごとで変遷したりする旨を述べた。
入れ子状に石の認識を規定したのも私だった。
私の構造の課題で言うと、私は発展段階的な図式で述べたため、一度その石が神聖視の領域に入ると、もうそこで固定化され、神聖視以外の領域に移ることができないかのような錯覚が確かに起こる。
私の文章化できていなかったところの思いとしては、その認識段階は人によって違うだろうし、時代ごと、時期ごと、もっと言えば時間ごとに変動して良い(つまり、時間と人という2つの基準を変えれば認識や類型は変化して良い)という考えではあったが、類型分類をしてしまう以上、極めて固定化されやすい危険をはらんでいたことは否定できない。
倉石氏のこの認識法は、柔軟性が増したものと理解することができる。
1つの石が、時代ごとや人ごとによって認識が異なるというような大きな括りだけではなく、たとえばある特定の一人の人の中でも、祭祀中と祭祀していないときで石への意識が異なる、朝と夜では意識が異なる、目に見えている時と見えていないときでは意識が異なるという、極めて微細な人と石の関わりが図式化できるのである。
これは、リアルタイムな人の感情の動き合いを表現できるモデルとなっている。
石を他の題材に変えても、通用する考え方だろう。
しかし、この尺度を用いて1つ1つの岩石の事例を総当たりしていったら、現状ではとりあえず私の手には負えるものではないことも付言しておきたい。まさに人の数だけ、時間の数だけ類型分類できるというパンドラの箱である。
(だから、私は無意識的に限界を感じ、発展段階的な入れ子の図式で考えたのかもしれない)
まずは、一つの事例を掘り下げて考察する時に、倉石氏のこのイメージモデルを私も参考にしていきたい。
九 石神と道祖神
第一節で問題提起した道祖神と石神の問題が、この最終節で帰結する。
道祖神となった石は、倉石氏に言わせればその時点でまずココロにかかわる石であったということになる。
特に、丸玉や性石・奇石の形をした道祖神は、祭礼がない平常時においても景観の中に埋没しにくく、ココロに関わる信仰が色濃いからだと指摘する。
像容碑や神名碑の形をとる道祖神も、本来形の見えない「たま(魂)」を顕在化するための一つの手段だった。
景観としての石を、どうにかこうにかして人が顕在化することで、人のココロの中に入ってくる。道祖神は、その傾向が高い存在なのかもしれない。
倉石氏はその一例として、石祠を道祖神としてまつる例にも触れている。
祠は資材であるので、祠は祭祀施設でその中に内在する「たま」が信仰対象であると捉えるのは私も同感なのだが、当事者は実際そこまで分けて考えていたのだろうかという疑問もある。
石に神名を刻んでその石を信仰対象として顕在化させたように、祠も神名や神仏図像と同じく「神が顕在化した形」の一つのあり方と直感的に信仰者が意識せず受けとめていたならば、祠も信仰対象の姿として認めることが、より実情に即しているのかもしれないとも思う(物品が擬人化されるような心理で)。
これは少し議論の方向が違う話なので、もう一度本筋に戻す。
倉石氏は、道祖神碑と自然石が並祀されている例をいくつか挙げ、岩石信仰由来の石と道祖神信仰由来の石がある段階で複合化・重層化し、道祖神は顕在化しているからずっと道祖神としての信仰を歩みつつも、自然石の岩石信仰的なココロがすべて失われたわけでもなく、道祖神信仰の中で併存しつづけてきたとまとめている。
石神信仰における自然石、道祖神信仰における自然石は、そういう意味ではどうにかこうにかして人が顕在化させようとした石というより、いやでも顕在化されてしまった石なのか。
自然物でも、巨石や奇岩、立地的な特徴があれば、まだ理由に説明はつく。嫌でも顕在化されてしまうからだ。
そうすると、最終的に謎が残るのは、ある人から見たら意識もしないような景観的な自然石が、なぜか特定の人にはいやでも顕在化され、ココロの対象となっている事例だ。
特定の人と言い切れる理由は、その人々がいなくなると、あっという間にただの石と化してしまうケースに多く出会ってきたことからも言える。
(忘れ去られた信仰、なくなった石などはその典型)
折口信夫が言うところの「巫呪者」の感覚がココロ化する瞬間についても、常人であるはずの研究者がもっと歩み寄っていく必要がある。
信仰の当事者、特に信仰の発起人は、大多数の人が見落とす、岩石の何かしらの側面に"過敏に"ココロを影響していると思うのである。
本稿で学んだモノ・コト・ココロという視点から、宗教者だけでなく、哲学者、文学者、芸術家たちの「常ならざるココロ」を探究することで、岩石信仰に近づいていきたい。