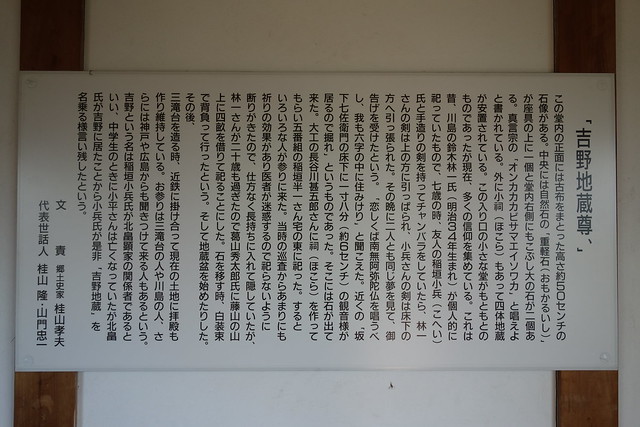同志社女子大学特任教授・吉野政治氏による著書。
国文学を専門とする吉野氏が、日本の古典から明治時代の鉱物学書にいたるまで、砂石・岩石・玉石に関わる記述をあまさず取り上げ、それを網羅しきった石の博物誌的な書である。
石の研究者としてのアプローチではなく、国文学から素材としての石を見たアプローチのため、その客観性が石の研究としては新しい流れになっている。
本書の前半部分「前篇 日本の鉱物観」が、私自身の興味関心と合致したので、前半部分を中心に勉強になったところを取り上げていきたい。
「大石(おほいし)」と「生石(おひし)」
古代語研究では、『古事記』に「意斐志(おひし)」、『日本書紀』に「於費異之(おひいし)」とある語が、大石を指すのか生石を指すのかで意見が分かれているらしい。
吉野氏自身も両説ともに一理あり判断しがたいようだが、他の論旨からやや「生石」派のようである。
「生石」はかつて柳田国男が「石が成長する伝説が多い」と指摘した生石伝説に連なる系譜の概念である。
生石の概念は石に意思を認めるものであるが、大石はどちらとも言い難い。大きい石としての石を想定しがちだが、大きな石への威容を込めた概念と考えると大石にも意思が込められた場合があるかもしれない。そこに注意したい。
砂と石の名前の分類整理
近代鉱物学の知識が入る前の日本語の中での石・砂の名称表現を、吉野氏は江戸時代の学者である佐藤信景『土性弁』の砂石の分類などを踏まえて、次のとおりに整理している。
- ス(沙/洲)・・・「スナ」は元々「ス」と呼んだ。砂そのものと、砂がある場所(=洲)も指す言葉だった。
- スナゴ(砂な子/洲之子)・・・ 「砂の子」なので、「ス」よりも微細なものを指した。
- マナゴ(真+スナゴ)・・・真に繊細な砂の子ということで、スナゴよりもさらに小さなものを指した。『萬葉集』のマナゴの用例はすべて浜辺・水辺の細かい砂として登場していた。
- イサゴ(石子)・・・石より小さいもの、あるいは小さな石。砂より大きいか砂と同じ大きさを指す表現だったかは諸説あり、吉野氏はス・スナゴ・マナゴとは別系統の言語ではあるが、砂と同じ大きさ程度のイシ系統の言葉であると考察している。
- マサゴ(真+イサゴ)・・・これまでの議論を踏まえると、スナゴとほぼ同じ大きさを指すイシ系統の言葉か。
- ミサゴ(水+イサゴ)・・・古典の用例が水の字を多く当て、水辺や水から出た石としての注釈が複数あった。
- イシ(石)・・・イサゴよりも大きいもの。つまり砂より大きいもの。イシゴとは親子の関係であり、イシゴが成長するとイシになるという考え方が見られるという。手の上に乗る大きさから、石の上に人が乗るぐらいの大きさまでが古典から読み取れるという。
- サザレイシ/ササライシ(磧石)・・・細かい石の意であるが、「磧」は「かわら(河原)」を指す語であり、磧石は河原の小石から由来している。
- イハ(磐)・・・イシが大きくなったもの。イハの大きい様子をイハホ(巌)として本来言葉を分けていたが、新しくても江戸時代にはイハとイハホは同義としてみなされた。
- トキハ(常+イハ)・・・常にあるイハのように、永遠性を表現した言葉。
- カチハ (堅+イハ)・・・堅いイハのように、堅固性を表現した言葉。
吉野氏は砂・石に関わる古語を総覧した結果、水とのかかわりが深いことに着目して、砂が水辺で成長して石になるという考え方がかつて根強かったのではないかという仮説を提唱されている。
まったくの主観ではなく、『萬葉集』など古代の和歌に歌われた石に川・海のモチーフがセットで使われていることや、 『和漢三才図会』に「土中・水中の石はよく育つ」「水中の細石が岩となる」「石の皮をはがすと枯れてしまう」などの記述が見られることを踏まえての主張である。
ヤマト朝廷の支配者層は「ものを言う石」を信じていなかった?
『日本書紀』一書第六に、高天原から見た葦原中国の様子を描写する以下の記述がある。
「葦原中国は、磐根・木株・草葉も猶し能く物語ふ。夜は熛火の若に喧響ひ、昼は五月蠅如す沸騰る」
記紀を編纂したヤマト朝廷の支配者層としては、祖先にあたる高天原の神々が葦原中国を平定した時の大義名分が必要だった。
その一つとして、葦原中国は岩や木や草葉が昼夜うるさくしゃべっているというのを、未開社会の証として記述した。それを啓発するための高天原の神々という構図である。確かにそう読めて興味深い。
吉野氏の指摘で注目したいのは、このような記述があるということは、当時のヤマト朝廷はすでに自然物がものを言うというアニミズム信仰を信じてはいなかった証拠ではないかという点である。
信じなかったというよりも、平定すべき先住民のアニミズム信仰を否定するためにこのような立場をとったという見方も取れる。
天津神が祭祀装置としての磐座系文化で、国津神が信仰対象とする石神系文化という二項対立の構図がすぐ頭に浮かぶ言説ではあるが、古代祭祀の研究や祭祀考古学の最新の研究も踏まえて、ここは安易に結論付けるべきではないだろう。
磐座が石神化して二分できない事例が多く、石神も国津神のものと決まっていなかったり、そもそも磐座と石神の先後関係はまだ証明されておらず、それを今残る文献だけで評価するのはまだ拙速と見たい。
仏教が教化しきれなかった列島基層の岩石観
中国由来の仏典・経典・漢籍では、木石を人の心を失った状態、死んだ状態としてたびたび表現している。
日本の奈良~平安時代の上流階級の文人たちは、こうした漢籍を忠実に由来して、人は木石ではない、木石は心を持たないというたとえを好んで用いた。
これだけ読むと、日本ではすでに岩石信仰は失われたと読みといてしまうが、そうではなく、心の深層には石が物言う往時の心性を脈々と続けてきたことを一部の文献から吉野氏は見つけ出している。
- 岩木にも物の心はありといへばさぞなわかれの秋はかなしき(鎌倉後期の歌集『夫木集』)
- 木石心なしとは申せども(略)石に精あり(江戸時代の謡曲『殺生石』)
- 松浦佐用姫がひれふりし姿は石になりにける(鎌倉初期の『曽我物語』)
- 明恵上人(1173~1232年)が中国の経典に「土で加持する」と書いてあったものを「土砂で加持する」に変え、イサゴ、スナゴ、細砂と形容される砂を実質的に使用した。
どれだけ外来の文化が流入して、表面上は木石心なしという概念が浸透したとしても、詩歌や物語などの文献の中で、木石に心は宿っているのではないかという期待を込める記述が見られると吉野氏は調査している。
このあたりは、かつて大護八郎が『石神信仰』(木耳社、1977年)で論じた、仏教の影響が及んでも水面下で日本古来の石神信仰が石仏と時に融合しながら現代まで持続したという考えの延長にあるものだろう。
石が無情のものとして比喩される時は多く「木石」がセットであることも仏典漢籍由来であることの表れで、日本列島における石へのまなざしは無情(感情がない存在)ではなくあえて言うなら非情(喜怒哀楽がない超然永遠としたもの)であると論ずるのが吉野氏の結論である。
非情とは、石の永遠性(トキハ)・堅固性(カチハ)を感情面で付託した場合の石の特性としてまとめることができるだろう。